Ciao!
スーツ離れの理由は単なる流行ではなく、働き方や価値観の変化に根差した現象です。本記事では、世代別の意識や市場の動向、再評価されるスーツの役割まで専門家目線で徹底解説。自分に合う装いを見つけるヒントが得られます。
スーツ離れが加速している現状とは

ビジネスファッションの象徴だったスーツが、近年、若者を中心に敬遠される傾向にあります。以前は「社会人ならスーツが基本」とされていましたが、今では「なぜ着なければならないのか」と疑問を持つ人が増えています。スーツは“着るべきもの”から“選ぶもの”へと変化しているのです。
市場データに見るスーツ需要の変化
経済産業省の調査やアパレル各社の業績からも、スーツ市場の縮小が明らかです。2010年代後半から減少傾向にあり、特に新型コロナウイルスの流行以降、テレワークの普及とともに着用機会が激減しました。青山商事やAOKIといった業界大手も、従来型スーツの販売数はピーク時の半数以下に落ち込み、カジュアルラインやセットアップへの注力を強めています。
2023年にセレブリックス営業総合研究所が実施した「業務中の服装に関する調査」によればスーツやセットアップを着用している人は全体のわずか29.8%。一方で「オフィスカジュアル(ジャケットあり・なし含む)」が44.9%を占めており、すでにスーツが多数派ではないことが明らかになっています。
なぜ今スーツが着られなくなったのか?
背景には、働き方の変化と価値観の移行があります。テレワークの定着により「人と直接会わない」業務が増え、動きにくく手入れの手間がかかるスーツは、現実的に不便な服となりました。
さらに、Z世代やミレニアル世代は「心地よさ」や「個性の表現」を重視し、スーツに代表される画一的な服装に違和感を抱く傾向があります。SNSや動画メディアの普及によって、“見られ方”がより自由になり、フォーマルすぎる装いは「気取っている」とすら受け取られる場面も出てきました。
こうした変化を受けて、スーツは単なるビジネスウェアではなく「選択肢のひとつ」へと再定義されつつあります。
若者とスーツの関係性

特に若年層において、スーツは「必要だから着るもの」から「着る理由が見つからないもの」へと移り変わっています。服に対する考え方そのものが、過去とは大きく異なっているのです。
10〜30代における着用率の変化
若者世代にとって、スーツはもはや日常的な服ではありません。2024年にクロス・マーケティング社が実施した「スーツに関する調査」によると、全国の20~69歳を対象とした中で、スーツを「年に1回以下しか着ない」と回答した人が過半数を超えました。特に20〜30代ではその傾向が顕著で、「まったく着ない」「年に1回未満」という回答が他の年代よりも多く、スーツ離れが世代的な現象であることがデータでも裏付けられています。
同調査では、スーツを直近1年以内に購入した人は全体のわずか13.3%にとどまっており、若年層を中心に「必要になってから買う」というスタイルが定着していることが分かります。実際、リモートワークや服装自由の企業に勤務する20代社員の多くが、就活以来スーツを着ていないという実情もあります。
こうした変化は、単に「着用しない」という事実だけでなく、スーツに対する認識自体が「特別なときだけの服」「フォーマルな場面専用の装い」へと変化していることを示しています。日常の中にスーツが存在しないことが、今の若者たちにとってはごく自然なライフスタイルなのです。
若者が感じるスーツへの心理的ハードル
若年層の声に耳を傾けると、「堅苦しい」「動きづらい」「洗濯が面倒」といった不満が目立ちます。さらに、「スーツを着ると自分が自分でなくなる感じがする」「言葉遣いや態度までかたくなる」という心理的な反発も少なくありません。
スーツは単なる服装ではなく、若者にとっては“自分らしさを奪う存在”と認識されていることが多いのです。
SNS・ファッション意識の影響
現代のファッション情報は、テレビや雑誌からSNSへと主流が移りました。InstagramやTikTokでは、ゆったりしたシルエットやカジュアルなレイヤードスタイルが多く支持され、スーツのようなフォーマルな装いは“古い”と見なされがちです。
人気インフルエンサーが「スーツは嫌いじゃないけど、自由がない感じがする」と発言すれば、それが若者の共感を呼び、着用離れをさらに後押しするという構図も生まれています。
世代別に見るスーツ離れの理由

スーツに対する意識の違いは、年代ごとに大きく分かれます。どの世代も同じようにスーツから離れているわけではなく、それぞれの背景に応じた変化があります。
ミドル世代(40〜50代)の変化と背景
かつて「スーツは社会人の常識」とされた世代でも、テレワークの導入や健康意識の高まりを背景に、日常的にスーツを着る機会が減少しています。とくに管理職や経営層では「必要な場面だけ着用する」というスタンスが一般化しつつあります。
シニア層に残るスーツ文化
60代以上の世代では、スーツは今なお“信頼の象徴”として重要視されています。たとえ仕事を引退していても、地域の会合や公的な集まりにスーツで参加する人が多く見られます。
しかしながら、この世代が第一線から退いていく中で、スーツ文化の継承が難しくなっているのも事実です。
世代間ギャップと価値観のズレ
スーツに対する価値観は、世代間で大きく分かれています。ミドル世代が「状況に応じて着るもの」と考えている一方で、若者は「個性を制限する服」と捉え、シニア層は「礼儀として当然」と受け止めています。
この価値観のズレは、職場の服装ルールや採用面接時の服装指導にも影響を与えています。たとえば、新卒が私服で面接に来た際に、それを好意的に捉える若手管理職と、常識を疑うベテラン人事の間で意見が割れる場面も少なくありません。
スーツ離れを語る上で、こうした世代ごとの背景を理解することは非常に重要です。自分がどの立場にいて、どの視点でスーツをとらえるかを明確にすることで、より柔軟で実用的なファッション選びが可能になります。
| 世代 | スーツへの価値観 | 着用頻度 | 一般的な印象 |
|---|---|---|---|
| 若者層(10〜30代) | 自己表現を制限される服装と感じる | ごく少ない | 古い・堅苦しい・必要がない |
| ミドル層(40〜50代) | シーンで使い分ける実用的な服装 | 減少傾向 | TPOに応じた装い |
| シニア層(60代〜) | 礼儀・信頼の象徴として不可欠な服装 | 週1回以上が一般的 | きちんとした印象・社会人の証 |
スーツは本当に「古い」のか?


スーツは「古くさい」「時代遅れ」と見なされがちですが、その評価は一面的すぎるかもしれません。今一度、その特性と現代とのギャップを見直す必要があります。
スーツの機能性・不便さに対する評価
ウールを中心としたスーツの素材は、実は吸湿性や耐久性に優れており、適切に管理すれば5年、10年と長く使えるアイテムです。ただし、毎日の着脱・クリーニングの手間や、夏場の蒸し暑さには課題が残ります。
ある営業職の男性(33歳)は「夏に汗をかいたまま1日過ごすのが苦痛」と話しており、利便性を重視する現代人にとっては、ややハードルの高い装いになっていることは否めません。
カジュアル化で失われたもの・得たもの
スーツを着ないことで得たのは「快適さ」「自由な発想」「個性の表現」です。ポロシャツやセットアップ、スニーカーでも違和感なく働ける環境は、特に若手世代にとって大きなメリットです。
一方、失われたのは「緊張感」「プロ意識」「場の格式」と言えるかもしれません。
自由な服装は歓迎される一方で、「信頼を得るためのツール」としての役割を果たせる服が求められる場面も、今なお存在しています。
服装の自由度が高まるほど、どんな場面でどんな服を選ぶべきか、個人の判断力が求められます。
「スーツは古い」と一線を引くのではなく、「どの場面で何を着れば自分を最も良く見せられるか」を考える視点が必要です。
再評価されるスーツ:変化する役割


スーツは単に着なくなったのではなく、「選び方」が変化しています。自分を魅せるためにスーツを使うという、新しい着こなしの潮流が広がりつつあります。
ファッションアイテムとしてのスーツ
ユニクロやZARAなどでは、ビジネスにも使えるセットアップが若者に人気です。素材や色合い、カッティングに変化を加えた「着やすいスーツ」が注目されており、特に20〜30代の男性を中心に、休日にジャケットだけ羽織るというスタイルも増えています。
スーツ=堅苦しいという固定観念が少しずつ崩れてきています。
オーダー・高級志向への回帰
一方で、「着る機会が減ったからこそ、良いものを選びたい」という意識も強まっています。量販型スーツではなく、自分の体に合った一着をオーダーするという選択肢が浸透しつつあり、オーダースーツ専門店の利用者数も増加傾向です。
| 価格帯 | 特徴 | 主な利用層 | 代表的なブランド例 |
|---|---|---|---|
| ~10万円 | 初めてでも手が届きやすい価格帯 | 若年層・20〜30代 | DANKAN、SADA、グローバルスタイル |
| 10〜40万円 | 生地や縫製の質が高く、長く使える設計 | 中堅ビジネス層 | 麻布テーラー、リングヂャケット |
| 40万円以上 | 一生モノとしての品質。完全フルオーダー | 経営者・富裕層 | 伊勢丹メイドトゥメジャー等 |
新しいスーツ文化の兆し
SNSではスーツを“かっこよく着こなす”ことが注目されており、あえて着ることで周囲と差をつけようとする動きも生まれています。OMO型(オンライン・オフライン融合)のスーツ店や、カジュアル仕様のオーダースーツ専門店の台頭は、新たな文化を象徴しています。
着用の選択肢がある時代だからこそ、“自分にとっての一着”を見つけてみてはいかがでしょうか。
スーツ離れの中で考える「着る意味」


スーツを着るかどうかは、単に会社のルールや周囲の空気に従うだけの話ではなくなってきました。カジュアル化が進む今、自分がどんな場面で、なぜその服を選ぶのかという判断がより重要になっています。
スーツを選ぶか、選ばないかの判断軸
「今日はスーツを着るべきか?」という問いに対し、今の時代はさまざまな答えが存在します。企業によっては完全に私服勤務を導入している一方で、来客対応や営業の場面ではスーツを推奨するケースも根強くあります。
判断軸の例として、以下のような要素が挙げられます。
- 相手に与える印象(信頼感・誠実さ)
- その場の空気(社内会議か対外商談か)
- 自分の役割(主役か、裏方か)
- 着用による気分やモチベーションの変化
自分がどう見られたいか、どんな立場で相手と関わるかを意識することで、服装の選択はより主体的になります。
「スーツだから着る」のではなく、「着る意味があるからスーツを選ぶ」ことが求められています。
TPOと自分らしさのバランス
TPO(時間・場所・状況)を意識することは、服装において基本中の基本です。ただし、それだけに縛られてしまうと、どこか「自分らしさ」が失われてしまうこともあります。たとえば、ネクタイの色や時計、靴などのアイテムで個性を表現すれば、堅苦しさを和らげながら信頼感も損ないません。
スーツを着ることは、単にルールを守る行為ではありません。それは、自分をどう見せたいか、どんな立ち位置で相手と向き合いたいかを考えるひとつの手段です。だからこそ、「似合うかどうか」より「どう着たいか」に意識を向けてみることが、これからの時代のスーツとの付き合い方なのかもしれません。
よくある質問
- スーツは何色が無難?
-
最も無難で汎用性が高いのは「ネイビー」または「チャコールグレー」です。これらの色はビジネス、面接、冠婚葬祭の場面でも違和感がなく、シャツやネクタイの色とも合わせやすいため、1着目として非常におすすめです。ブラックはフォーマル寄りになりすぎるため、日常の仕事用としては避けたほうが無難です。
- スーツにベストを着る理由は何ですか?
-
ベストを加えることで体全体のシルエットが整い、よりフォーマルで洗練された印象を与えられます。とくに座ったときにシャツが見えにくくなるため、品格を保ちたいシーンに最適です。また冷暖房対策にもなります。
- スーツは毎日同じものを着てもいいですか?
-
見た目は問題なくとも、生地の劣化や臭いの蓄積を防ぐため、毎日同じスーツを着るのは避けた方が望ましいです。最低でも2着を交互に着回すことで、スーツの寿命を延ばし、常に清潔感を保てます。また、汗を吸った裏地が乾く時間を確保することも重要です。
- スーツの大手4社は?
-
青山商事、AOKI、コナカ、はるやま商事の4社が日本の主要スーツ量販チェーンです。価格帯・サイズ展開が豊富で初心者にも安心です。
- スリーピーススーツがダメな理由は何ですか?
-
スリーピーススーツ自体に問題はありませんが、場面によっては「目立ちすぎる」「やりすぎ感がある」と受け取られることがあります。たとえばカジュアルな社風やラフな会合では浮いてしまうことも。また、ベストが体型に合っていないと窮屈に見えるため、着用時にはサイズ感とTPOへの配慮が必要です。
- スーツに白シャツを着るのはなぜ?
-
白シャツは清潔感と信頼感を強く印象づけるため、スーツスタイルでは定番とされています。どんな色のスーツやネクタイとも調和しやすく、場面を選ばない万能アイテムです。特に面接やフォーマルな商談では「誠実さ」を伝える手段として、白シャツの選択が最も無難で安心されやすいとされています。
スーツを着る意味が変化する今、自分にとって最適な装いを見直すことが大切です。スーツ離れの理由を理解すれば、形式ではなく目的で服を選ぶ視点が得られ、より自由で洗練されたスタイルが築けます。
Grazie!

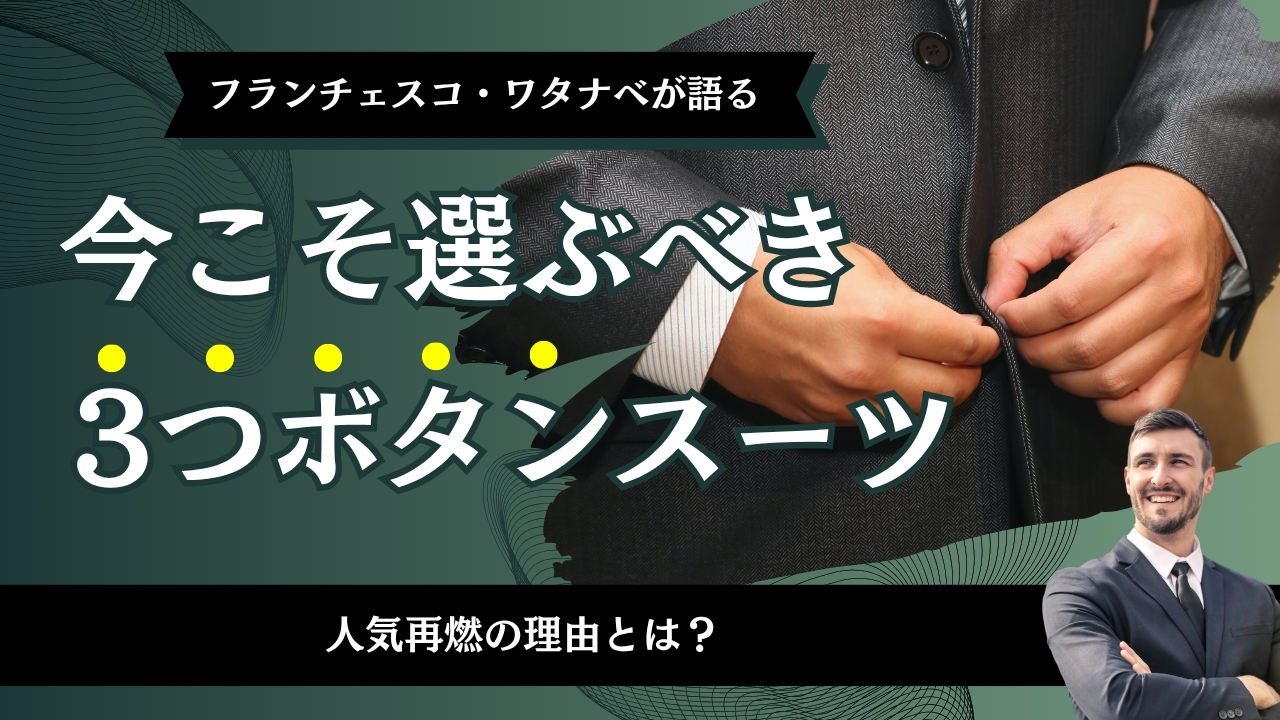


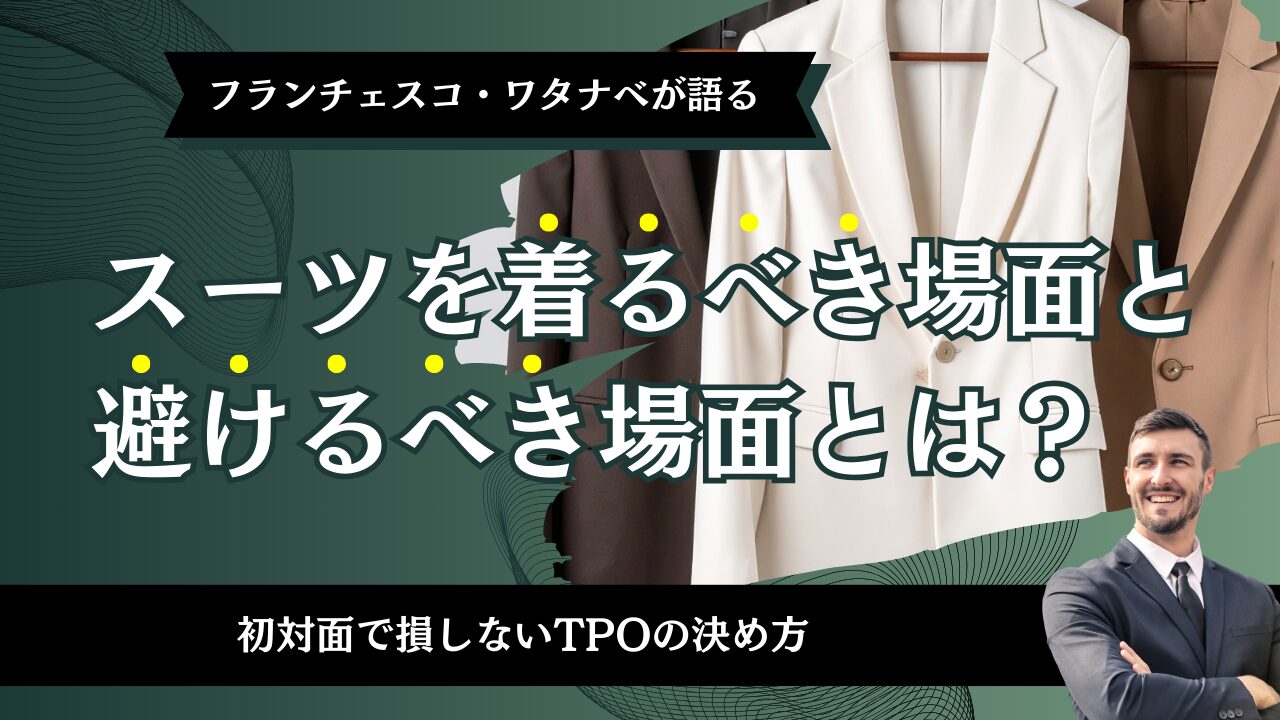
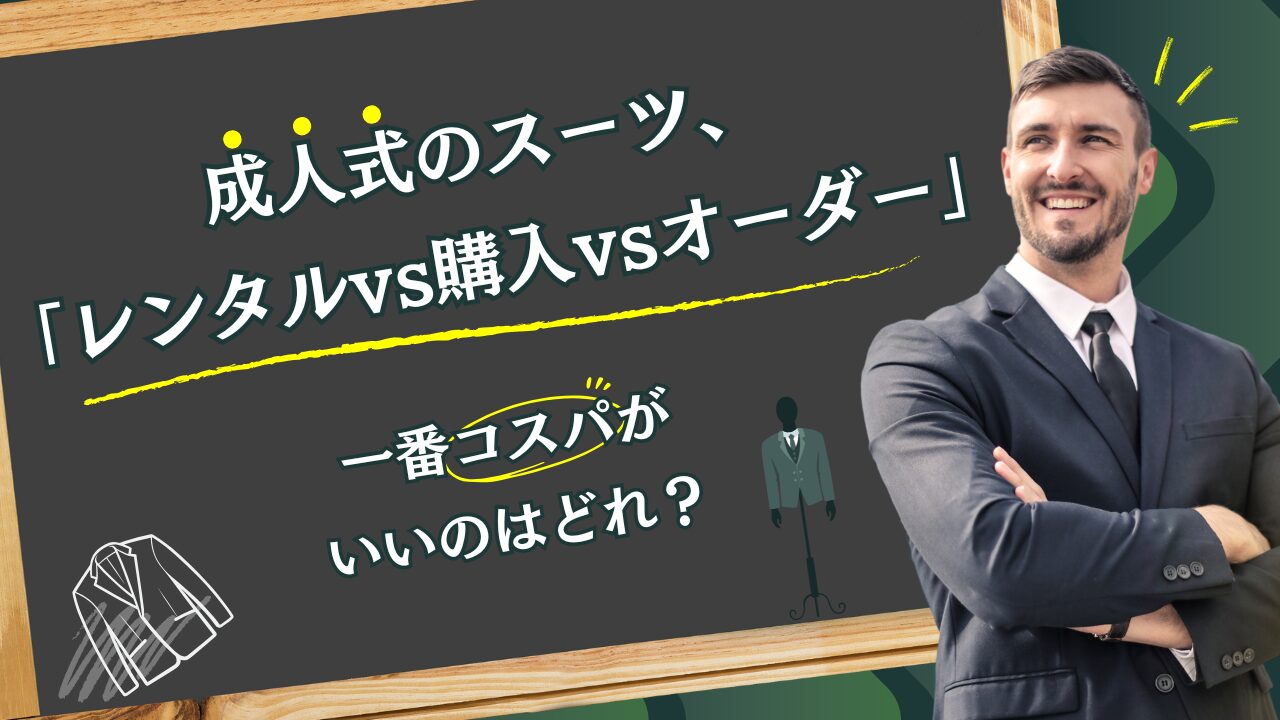
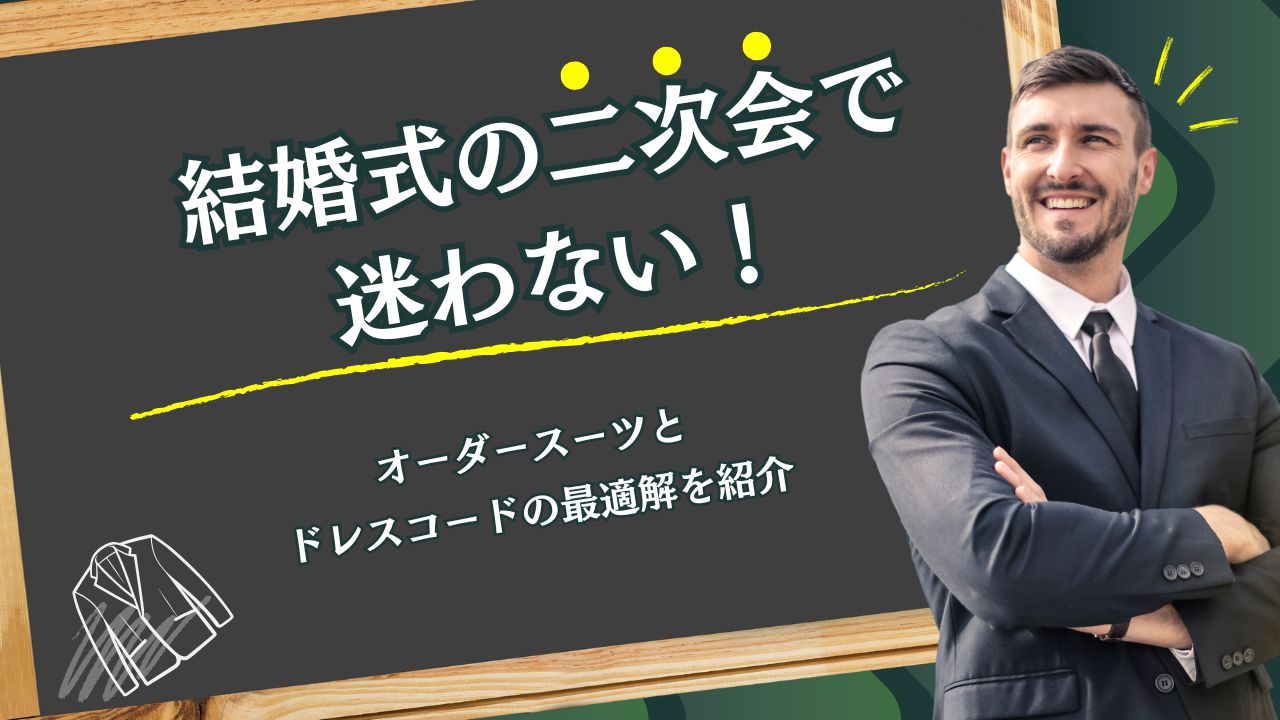

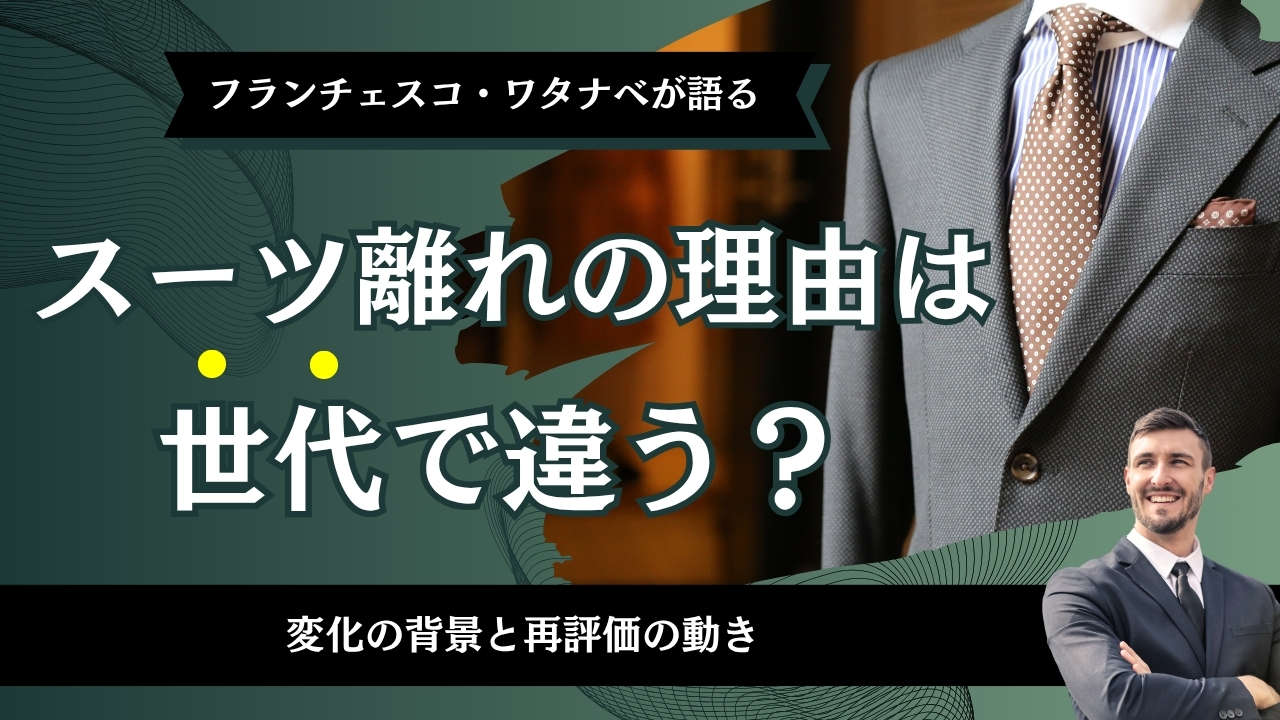
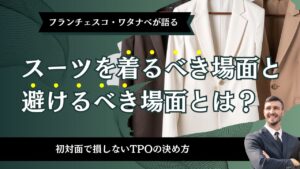
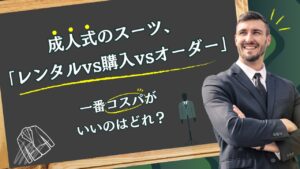
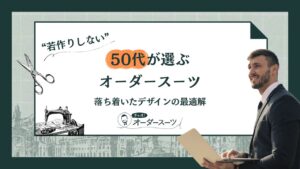
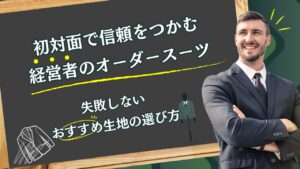
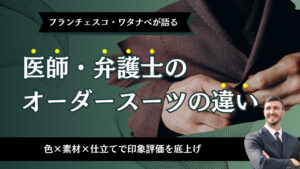
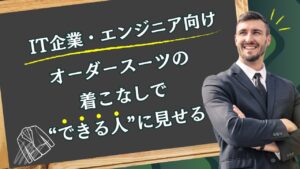
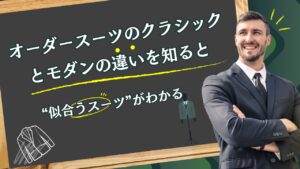
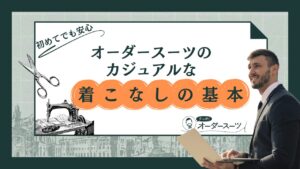
コメント